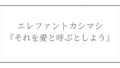エレカシの顔であるVo. Gt.宮本浩次のことを、”変わっている”と評する人は多い。まあ実際、いい意味で人とはちがう独特の感性を持ち合わせていなければミュージシャンを長年続けていくことなんてできないんじゃないかと思うので、彼がいい意味で「変わっている」のはたしかだろう。
インターネット上でエレカシに関する過去の情報を辿っていくと、「宮本浩次 キレる」「宮本浩次 マイク投げ」といった検索ワードがわりと高頻度で目に入る。調べてみると、どうも2002年に開催されたLiveHouseTourの出来事らしかった。
アーティストが商売道具であるマイクを投げるとは…?
2002年当時の私はまだエレカシファンではなかったため、この出来事に関する詳細や現場の空気感みたいなものが全くわからない。が、とりあえずこの「マイク投げ事件」についてある程度ネット上に残っている情報をもとに、自分なりに思ったことや考えたことを今回は書いてみようと思う。
エレカシライブ『LiveHouseTour2002』にて起きた「マイク投げ事件」とは
「マイク投げ事件」が起きたのは2002年のこと。もう20年以上も前の話だ。
調べたところによると、エレファントカシマシLiveHouseTour2002は非常に良いライブだったらしい。演者と客側の双方がともに同じ方向を向いて白熱し沸き返り、互いを高みへと誘うようにはたらきかけ、皆が一体となっていた、エレカシ史上かつてなかったほどの盛り上がりだったという内容のライブレポが多数見受けられた。
そんななか、”事件”は『ファイティングマン』の演奏中に起こってしまったのだという。
Vo.の宮本氏が歌唱中に突然、Dr.の富永さんのほうに向かってマイクを投げつけたのだ。(あくまで「トミさんのいるほうに向かって」であり、トミさん自身を目掛けて投げつけたわけではない)
会場は水を打ったように静まり返り、エレカシメンバーも演奏を中断した。マイクを投げた宮本浩次に皆が注目したとき、彼はこう叫んだのだった。
「あなたの力が必要です!あなたのドラムが必要です!ドラムはあなたしかいません、ボーカルもわたししかいません!」
「おまえの力が必要だ!!」
(※台詞はニュアンスです)
会場には再び熱が戻り、演奏が再開した。この”マイク投げ事件”があった後は、正直それまでの時間以上に盛り上がったし楽しめた、というような声も多い。
”マイク投げ”についていちファンとして思うこと

宮本浩次はなぜ、マイクを投げるという暴挙に出たのだろうか。暴挙、と表現すると語弊があるのかもしれないが、やはりアーティストが商売道具であるマイクを投げるというのは少なくとも普通じゃない行為ではあると思うし、傍からみるとびっくりする。
たとえばテニスの大坂なおみ選手が試合中、テニスコートにラケットを投げつけて壊してしまうという場面があったけれど、個人的にはこの例と同じくらい驚いた。これは批判する意図ではなくて、マイクやラケットという、自分の能力を表に出すために不可欠なアイテムを投げてしまうという行為にただただ”びっくりした”のだ。
ライブについて少し補足すると、宮本氏がマイクを投げる直前、ドラムの音の遅れとズレがかなり目立っていたらしい。ドラム側はひたすら演奏に熱中していてそのことに気づかず、それに対し徐々に苛立ちをつのらせたボーカルがついに爆発した、という経緯だった。
この件を聞いて個人的に連想するのは、宮本浩次が『かけだす男』をウォークマンで聴いた際に音の仕上がりに納得できず、その場でウォークマンを道に叩きつけて壊してしまったというエピソード。
いや、このエピソードすごく好きなんですよね。ザ・ロックミュージシャンとでもいうべきか、痺れるくらい”真剣さ”が伝わってくるし、文字通り一寸の妥協も許さないくらい真摯に音に向き合っているということが分かる。
つい大坂なおみ選手を例に出してしまったけれど、試合当時は(もしかしたら今も)ラケットを投げた彼女を非難する声もたくさんあったはずだ。
私は別にテニスファンではないし、テニスについて全く詳しくはないから、スポーツ選手が闘いの場でする一挙一動にどんな理由があるのかは正直わからない。
ただ、お茶の間で彼女の活躍をみていて、彼女がテニスというボールゲームに職人的に真摯に向き合っていることくらいは知っているつもりだ。
アーティストにしても、またスポーツ選手にしても、どれだけ真剣に取り組んでいようが、明確な結果を出さない限りは世間からの評価は得られない。”マイク投げ”や”ラケット投げ”のように、時には真剣さが裏目に出て世間から叩かれることもあるかもしれない。真面目で不器用な人ほど誤解もされやすいのが世の中というものである。
そんなときは一人のファンとして、表面上の出来事だけではなく、そこにある真意みたいなものを決して見落とさないようにしたいなあと私はつくづく思うのだ。